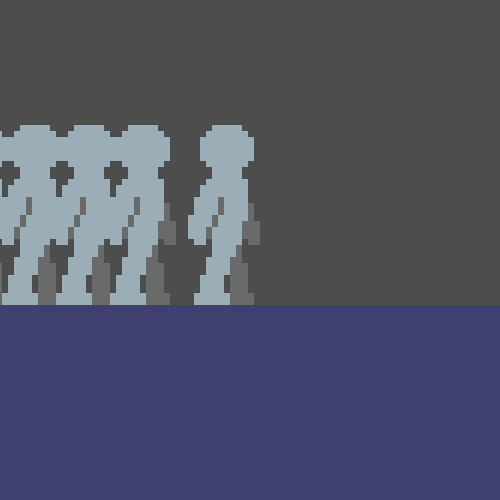
はじめに
「地獄、それは他人」であり
「悪の凡庸さ」や「コモンズの悲劇」は存在し
「他者の倫理」は考慮されない
未プレイの方へ
本作品は既に終わってしまっている。
文末には本作の企画書が添付してある。ゲームや設定等の内容詳細はそちらから確認できる。
このゲームの意図について
このゲームはプレイヤーを楽しませない
実験的アンチゲーム・アート「退屈な橋渡し」に触れていただいたことに、まず、感謝を述べたい。
そして、もしプレイヤーがこの作品をプレイして「退屈だ」「不親切だ」「楽しくない」と感じたのであれば、それはある意味で、プレイヤーに私の意図が正しく届いた証拠なのかもしれない。
このゲームは、プレイヤーを楽しませるために作られてはいない。 本作は、私たちが生きるこの世界の「ある側面」を映し出すために設計された一つの「鏡」である。
始まりは「痛み=理不尽・無配慮」
その前にまず伝えておくことがある。本作「退屈な橋渡し」を創作した動機は「痛み」にある。この痛みとは、世に蔓延する理不尽さや、他者への無自覚で無配慮な振る舞いに対して、tdhrの純粋すぎる(あるいは幼いままの)魂が感じたものだ。
理不尽さや無配慮の、その一つ一つが、誰かの道を静かに、そして確実に削り取っていく。
「この事実になぜ、気づかないのか」という気持ちに一つの形を与えたいという欲求がこのゲームの出発点となった。
「鏡」としての意図
しかし私はこの作品を通して、何かを声高に主張したり誰かを教育したりするつもりはない。私の意図は、ただこの世界の構造を模した一つの「鏡」をプレイヤーの前にそっと差し出すことだけである。
このゲームの最も重要なルールは(第一世界までではあるが)意図的に、プレイヤーに知らされはしない。次に訪れる顔も知らぬ誰かの世界を、プレイヤーの行為が不可逆的に変えてしまうという事実。これは、自らの行動が他者に与える影響(外部性)が、意図的に不可視化されたシステムと言えるだろう。
プレイヤー自身がその真実に自力で「気づく」こと。あるいは気づかないまま通り過ぎていくこと。これらのプロセスそのものが、この作品がプレイヤーに提供しようとしている唯一の体験だ。
世界への静かなメッセージ
このゲームにおける一度踏むと崩れる脆い「橋」。それは我々が共有するこの社会や環境そのもののメタファーに他ならない。 我々は皆、常に、この有限で脆い橋の上にいる。そして多くの場合、自らが渡り切ることだけに集中し、その行為が橋そのもの(=誰かの未来)を少しずつ破壊しているという事実には気づかない。
プレイヤーが取ったその何気ない一歩は、本当にそのプレイヤーだけのものであろうか。 本作は、その静かな問いを言葉ではなく体験としてプレイヤーに投げかける。
それでも祈る
しかし、この作品は世界の残酷さや人間の無自覚さを、ただ告発するためだけにあるのではない。その絶望的な構造の中に私は一つのか細い「祈り」と「希望」を込めた。前者はゲーム内に文字通り登場する。「祈り」だ。
それは、橋を渡り切ったほんの一握りの誰かが、この世界の真実に「気づき」、そして行動するかもしれないという人間性への信頼である。 喝采も栄光も報酬もないと知りながら、自らの「時間」という二度と戻らない最も貴重なコストを支払い、次に渡る見知らぬ誰かのために、新しいブロックを遺していく。
誰にも知られることのないその孤独で献身的な行為。それこそが、このあまりにも退屈で理不尽な世界に、私が唯一灯したかった希望の光だ。
確認
そう、私が本当に求めていたのは、そのような人が確かにこの世界に存在することを確認し、それを互いに共有することにある。
つまり、世の中には、他人の理不尽に気付きながらも心折れずに支えること(=橋渡し)ができる人がいるかもしれない。それを私が認めることで彼らの絶望が少しでも軽くなれば良いし、私も希望を持つことができれば嬉しい。
以前、tdhrが作成した「善意の花」との一番の違いはここにある。人間が普遍的に兼ね備える理不尽や無配慮、欺瞞をに明らかにするのではなく、その陰にある存在を大事にしたかったのだ。
もちろん、このゲームには答え・正解といったものは存在しない。プレイヤーがこの「退屈な橋渡し」を終え、ブラウザを閉じた後、プレイヤーの心の中に何らかの感情や問いが芽生えれば、それだけで私の目的は達されている。
結果と考察
プレイヤーの類型
プレイヤーは全部で大きく4つの類型に分別される
類型A:無自覚な通行人=橋を十分に救済しなかったプレイヤー
類型A-1:ルールを完全に把握できなかったプレイヤー
類型A-2:ルールを把握したものの救済には至らなかったプレイヤー
類型B:無配慮な破壊者=橋の破壊を目的としたプレイヤー
類型C:献身的な救済者=橋を十分に救済したプレイヤー
類型D:運が悪い人=中途半端な状態でプレイすることになったプレイヤー
結果一覧
第一世界
総プレイ人数:3
- 類型A-1:1名
- 類型A-2:1名
- 類型B:1名
総救済回数:1
総破壊回数:149
稼働期間:2025年6月27日00:18:00 〜 2025年6月28日 00:15:48
第二世界
総プレイ人数:6
- 類型A-1:2名
- 類型A-2:2名
- 類型B:1名
- 類型C:1名
総救済回数:21
総破壊回数:171
稼働期間:2025年6月28日 00:01:09 〜 2025年6月28日 09:14:35
第三世界
総プレイ人数:5
- 類型A-1:2名
- 類型B:1名
- 類型C:1名
- 類型D:1名
総救済回数:12
総破壊回数:140
稼働期間:2025-06-28 20:46:00 〜 2025年6月28日 23:17:03
考察
考察にあたって
はじめに断っておくが、これは極めて少ないサンプル数に基づいた、科学的厳密性には耐え得ない一つのスケッチである。しかしこの小さな社会実験は、我々の世界を映し出す痛烈な寓話(アレゴリー)としての役割を果たせるかもしれない。
第一世界:絶望
- 総プレイ人数:3 / 救済回数:1 / 破壊回数:149
この実験における完璧な対照群・基準が第一世界である。
それは、このシステムが何の外的影響もなく自然な状態に置かれた時、いかに早く、そして一方的に崩壊へと向かうかという冷徹な基準値を示した。
特筆すべきは、たった一人の「類型B:無配慮な破壊者」の存在が、他の二人の行動(あるいは、行動の欠如)の結果を、完全に無意味にしてしまったという事実である。これはたった一つの、純粋な、あるいは、無邪気な悪意が、脆弱なコミュニティをいかに容易に機能不全に陥らせるかという社会の縮図と言える。
この救いのない結末こそが「果たしてこの世界に希望はないのか?」という、次なる世界への根源的な「問い」を生んだ。
第二世界:救済
- 総プレイ人数:6 / 救済回数:21 / 破壊回数:171
第二世界はこの三部作の転換点となる。ここで初めて「類型C:献身的な救済者」の出現を目撃する。
この記録の最も胸を打つ点はその救済と破壊の数の非対称性である。「破壊回数:171」という圧倒的な破壊の奔流。それは一人の破壊者と四人の無自覚・無関心な人々によって生み出された。 その中で、たった一人の救済者が、21回もの、退屈で報われることのない、祈りの儀式を孤独に執り行っている。
これは私が求めていた、圧倒的な不条理を前に、それでもなお自らの信じる気高い行いを、ただ、淡々と続ける、一人の人間の魂の記録であると言える。(もちろん、この解釈自体が作者である私の「祈り」が過剰に投影された結果である可能性も、自覚せねばならない)それでもなお、第一世界が「問い」を提示したとすれば、第二世界は、「絶望的な状況下でも徳は存在しうる」という「答え」を示した。
第三世界:最終結果
- 総プレイ人:5 / 救済回数:12 / 破壊回数:140
救済者が再び現れている。彼の善性が一度きりの気まぐれではなく、ある種の態度として存在することをこの記録は示唆している。
同時に「運が悪い人(類型D)」という新しいプレイヤー現れた。彼は既に崩壊しかけた世界に生まれ落ちてしまった、罪なき犠牲者・被害者である。
これは、個人の悪意や善意といった二元論では捉えきれない、システムそのものが生み出す「構造的暴力」の存在を可視化させた。自らの意思や責任とは無関係に、ただそこに生まれたというだけで不利益を被る、声なき被害者の存在をも描き出したと言える。
まとめ
世界を無自覚に破壊する人間は、常にどこにでも現れる。そしてそれらが大多数である。
意図的に破壊する人間さえ存在する。
そして、そのシステムの歪みによって意図せず不利益を被る人々もいる。
しかし、世界を見返りなく救おうとする気高い人間も少なからず存在する。祈りは確かにそこにあった。
雑感
理不尽や無配慮を忌避する自分が、なぜ、それを真正面から受け止める羽目になる作品を提示してしまったのか。
かなりの自傷行為である。
最後に
もう1度だけ、橋をリセット・修復しておきました。
好きに遊んでください。
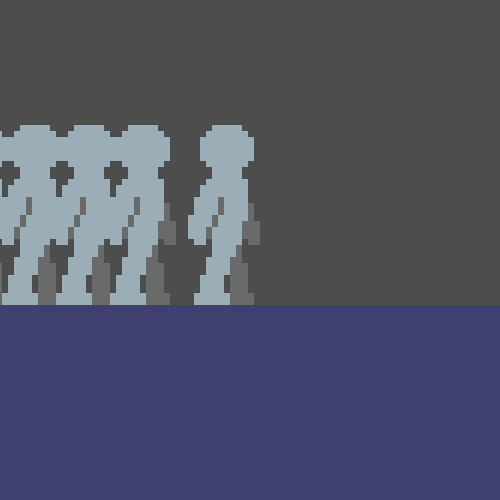
付録:企画書
ゲーム企画書:「退屈な橋渡し」
1. 情報
タイトル: 退屈な橋渡し (英語: The Tedious Bridging)
ジャンル: 実験的アンチゲーム / アートゲーム
プラットフォーム: Web (PC/モバイルブラウザ)
使用エンジン: Godot Engine (v4.4.1)
作成日: 2025年6月27日
2. コンセプト
「退屈な橋渡し」は、プレイヤーの何気ない行動が、顔も知らぬ他者の体験を不可逆的に、そして静かに変容させていく様を描く、非同期マルチプレイ型の思索的ゲームである。
プレイヤーは、一度踏むと崩れる脆いブロックでできた橋を渡る。その行為は、必然的に、後に続くプレイヤーの道を困難にする。世界は、プレイヤーたちの無自覚な往来によって、ゆるやかに、そして確実に崩壊していく。
しかし、ごく一部の「気づいた」プレイヤーは、多大なコスト(=時間)を支払うことで、後に続く誰かのために、新たな足場を遺すことができる。これは喝采も報酬もない孤独で献身的な行為である。
本作は、エンターテイメント性や達成感を意図的に排し、「社会的エントロピー」「見えざる他者への想像力」「利他行為の本質」といったテーマを、ゲームという体験可能なメディアを通して、プレイヤー自身に問いかける。
3. 思想的背景
本作は、「世の中の理不尽さ、他人への横暴・無配慮」に対する根源的な問いから出発した。その問いに対する直接的な答えを示すのではなく、プレイヤーがその構造の一端を担うことになる鏡としての世界を構築する。
プレイヤーの行動は、常に、まだ見ぬ誰かへの影響と地続きである。この見えにくい因果関係を体験することで、プレイヤーは、現実社会における自らの行動が持つ意味について、内省を促される。これは、ゲームの形をした、我々の時代に対する一つの痛烈な寓話(アレゴリー)である。
4. ゲームメカニクス
4.1. 基本構造:崩壊する橋
世界は、縦5ブロック × 横30列のブロックで構成された、一本の長い橋が主な舞台となる。
全てのブロックは、プレイヤーが一度踏むと、破壊され、消滅する。
プレイヤーは、3ブロック分の高さの段差であれば、ジャンプで飛び越えることが可能。これにより、プレイヤーは、最小限の破壊で進むか、意図的にブロックを破壊するか、あるいは何も気づかずただ進むかという、選択が生じる。
4.2. 非同期システム:世界の記憶
橋のブロックの状態は、サーバー上のデータベースに記録され、全プレイヤー間で共有される。
データベースは、単なるブロックの有無(状態)を記録するのではなく、どのアクション(破壊/創造)が、どのプレイヤーIDによって、いつ(タイムスタンプ)行われたかというログを、永続的に記録する。
4.3. 救済行為:献身的な苦行
橋を渡り切ったプレイヤーは、「救済」の選択肢を与えられる。
救済とは、30列の中から任意の1列を指定した後に祈るボタンを押し、ただひたすらに30秒間待機するという行為である。
この苦行を終えたプレイヤーは、その列にブロックを一つだけ追加することができる。
4.4. 祝福システム:私的な啓示
上記の救済行為を行ったプレイヤーには、公的な報酬は一切与えられない。
ただし、救済行為の回数に応じ、作者(tdhr)からプレイヤーへと、それぞれ異なったメッセージが表示される。
5. アート & 演出
5.1. プレイヤーキャラクター
「シンプルにデフォルメされた人」を素体とする。目や口などの感情を読み取れる特徴は、一切排されている。キャラクターの材質は、世界のブロックと同じ、石や風化した土のような質感を持つ。あくまでもプレイヤーは、世界に存在する有象無象の1人に過ぎない。
5.2. UI / テキスト
ゲーム開始前の説明文は、以下のものに限定する。
操作説明と「橋は一度踏むと壊れます。場合よってはクリアできないゲームかもしれません。」の文章。
このテキストは、世界の物理法則を明確に示しつつ、クリアできない場合がある、という警告によって、プレイヤーの心に、説明不能な要因の存在を暗示し、問いを植え付ける。
6. 技術仕様
エンジン: Godot Engine v4.4.1以降
レンダラー: GL Compatibility。グラフィックの性能よりも、Web/モバイルにおける互換性とアクセシビリティを優先する。
データベース: MySQL 8.0。行動ログ、橋の状態、プレイヤー統計の3つのテーブルを用意。PHPファイルを通じてGET/POSTで対応。

